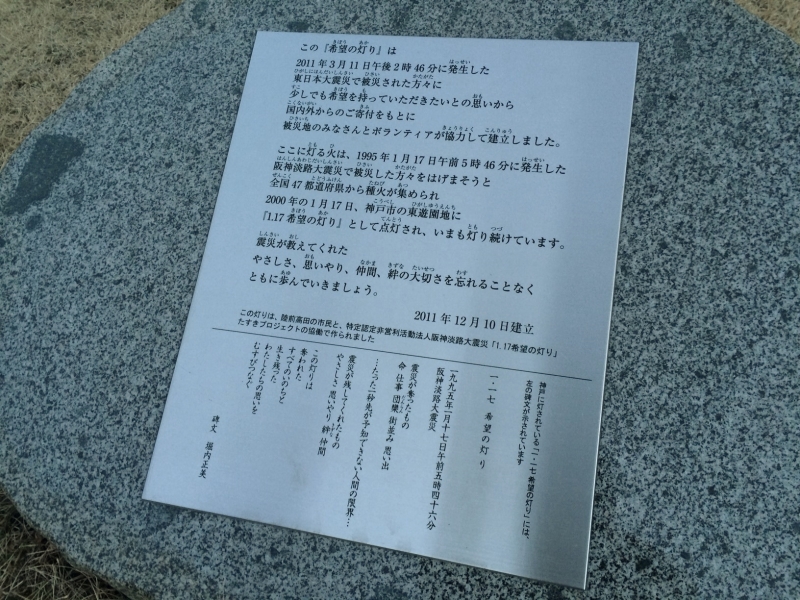前編を記したのは去年のことだった。文末には「記事を追加して再送します」と記している。それから1年。阪神・淡路大震災から20年。今年はメディアも大々的に取り上げる予定らしい。テレビや新聞ではすでに特集がスタートしているところもある。大手サイトでも特別仕様のページを用意しているなどと伝わってくる。
震災の記憶を風化させないために――。表向きはそういうことなのだろう。しかしどこかに「20年の節目」「これが区切り」という含意を感じてしまうのは、センシティブに過ぎるだろうか。いや、それ以前に「20年目のその日」だからといって、こうして記事を書いている自分はいったい何者なのだろうか? ごくりと唾を呑み込む喉の奥に苦いものを感じる。
熱いコーヒーのありがたさすら解っていなかった
東日本大震災で被災した地域では、阪神や関西からやってきたボランティアの人たちがとても多かったという。自分もいくつかのグループに出会った。たとえば「がんばろう!石巻」の看板での3.11追悼式典に、あたたかいコーヒーを毎回届け続けてくれる神戸・長田の人たち。たとえば大槌の神社で毎年元日にうどんやお餅、たこ焼きなどの炊き出しを行っている大阪の生協の人たち。その人たちは、立ち話には答えてくれるのだけれど、「何という団体なんですか」など聞いても、「いえいえ名乗るような者じゃないから」と話をはぐらかす。取材なんて勘弁してよと言う。
取材を拒まれているのに「そうだよなあ」と納得してしまうのはどうしてなんだろう。自分もそうありたいと心のどこかで思ってしまうのはなぜだろう。彼らはきっと、「もう大丈夫です」と被災地の人に言われるか、彼ら自身が納得するまでは、黙々と東北を訪問し続けるのだろう。
2年目の3月11日、「がんばろう!石巻」の黒澤さんが言っていた。「神戸の人たちは知っているんだよね。熱いコーヒーのありがたさを」と。
その言葉がいまは、こんなふうに聞こえてしまう。「彼らは風化のつらさを知っているんだよね」と。
昨年の1月17日に前の記事を上げて、その後ずっと書かなかったのは、神戸や西宮で経験したことを、さも「見てきました」というようなスタンスで書いた自分自身にウソとか、その他諸々のイヤなものを感じたからだと思う。
被災した美術館の「取材」という目的で被災地に入っていった自分は、なんらボランティア的なことをするでもなく、関係者の話を聞き、町の写真を撮っていただけだった。なかなか目にすることができないものを見て来たい。そんな野次馬根性がほとんどだった。そりゃ、出発前にはいろいろな場面を想像はしていた。しかし現地に入ると、神戸の人たちと話しをするとか、時間をつくって何か手伝うといったことはなかった。どう話しかけていいのかすら分からなかった。
被災地の人たちからすれば、自分など、いてもいなくても変わらない空気のようなものだっただろう。いや、被災地にいるというだけで、貴重なおにぎりや飲み物をコンビニで購入して物資を食いつぶすし、仮設トイレを使ったりもする厄介者でしかなかった。
空気の色まで冷え込んで見えた室内
しかし、20年前にそんな迷惑をかけたのだから、せめて見たことを伝えたいと思うのだが、実のところ大した話ができないのだ。いまはそれがとても申し訳ない。
数カ所取材して回った美術館では、展示室や収蔵庫の惨状や、建物の被害について説明してもらったが、それよりも何よりも記憶に残っているのは、話を聞いた事務室の片隅の光景だ。たいへんな時に押し掛けていったにも関わらず、「ガスがまだ来ていないので、寒くて申し訳ない」と恐縮されながら(それに対してこちらも一応カタチだけは恐縮し返しながら)、まだ散乱した書類が一部片付けられていない部屋で取材したこと。感覚としての寒さの記憶はあまりないが、話してくれた学芸員さんが革のコートにマフラーまでぐるぐる巻きにして、寒そうに体を丸めていたその姿は忘れられない。(彼の額には、震災当日に自宅で怪我をしたという傷跡が、まだ生々しかった)
どの美術館を訪ねても、震災で交通が寸断していたり、家族のことがあって職員がなかなか出て来れないという話だった。何とか駆け付けた館長や学芸課長といった幹部が、ほんの数人の職員と手分けして、少しずつ片づけを進めているという段階。建物の安全性が確認された美術館では、ロビーが避難所として使われているところもあった。同行した雑誌社の編集さんたちと「まだ詳しく話を聞かせてもらえる時期じゃなかったね」と話し合って、取材の最終日、3日目は、アポが取れている1カ所の他はほぼ個別行動になった。
その日の昼過ぎから三宮の街なかを歩き回って、テレビ映像や写真で繰り返し伝えられていた三菱銀行の兵庫支店にも足をのばした。西宮や東灘、灘周辺で民家が倒壊している姿も衝撃だったが、神戸の街の中心で大きなビルが何棟も壊れたり潰れたり傾いたりしている光景はショックという他ないものだった。
話しかけることすらできない
パンケークラッシュ(中間階が潰れて天井と床が合わさってしまうような激烈な破壊)を起こしているビルの向かいに、コーヒー1杯100円で営業している喫茶店があった。入り口のドアには、「この建物も倒壊の恐れがあります」と貼り紙されている。薄暗い店内がほぼ満席になるほどのお客さんがいたが、話し声はほとんどしてこない。いかにも新聞記者風の人も数人いた。店の主に話を聞こうと思ったが、「倒壊の恐れがあるって書いてますが…」「たぶん大丈夫だろう」「そうですか、頑張ってください」くらいのやり取りしかしなかった。
夕方になって、待ち合わせをしていた西宮方面へ自転車を走らせていく途中、大通りに面した小さなアーケード街がいくつか目に入った。入口のアーチからして壊れてしまっているところ、入口は無事に見えるのに、路地には建物が倒壊していて人が通ることすらできないようなところもあった。いろいろな建物が、予想もできない形で破壊されていた。
国道は支援車両やマスコミの車、ゼネコンの車で大渋滞が続いていたので、国道にほぼ並行して走る県道を地図を見ながら通っていくと、所々に公園がある。どこも避難所になっているようで、自衛隊色のテントがたくさん立てられていた。外で夕食を作っている人々の気配も感じられた。しかし、とてもその場所に入っていくことはできなかった。
自分が回った町や施設には暖房は皆無で、西宮あたりから電車に乗るまであたたかい空気を感じることはなかった。すでに電気は復旧しているはずなのに、町全体が薄暗くグレーがかっていた。それがどうだ、大阪の梅田に到着すると街はきらびやかな電飾で輝き、駅前は人波であふれていた。白熱電灯の光がこんなに明るくあたたかいものかと驚いた。道行く人がみんな幸せそうな表情に見えた。そのギャップが残酷なほどに鮮やかだった。
震災後初めて被災地に入った2月初めの3日間は、冷たくて埃っぽい風を感じて帰ってきただけだった。
ガラスが割れたまま開廊していたギャラリー
初回に取材らしい取材ができなかったので、2月の末には再度阪神地区に出かけている。その時には美術館の職員の多くが出勤可能な状態になっていて、それぞれの施設で詳しく話を聞かせてもらうことができた。西宮の美術館のロビーはまだ避難所のままで、パーテーションもない場所に避難してきた人たちがすし詰め状態で起居していた。
学芸員さんの表情に少し明るさが戻って来つつあるように見えたのに安心したが、話しの内容に明るさはあまり感じられなかった。そんな中、2回目の最終日、編集さんに「いいところを見つけた」と袖を引っ張るようにして連れて行かれたのは、三宮センター街(もしかしたら元町かもしれない)のギャラリー新光。大きなガラス窓が割れたままの店舗で個展が開催されていた。画廊の中には何人ものお客さんの姿まであった。その光景に自分まで勇気づけられた思いがした。
2回の取材でつくった記事には、こんな一文が記されていた。
「今回の地震ではっきりしていることがひとつある。地震に対してどんな備えをすればいいか、パーフェクトな解答はないということだ。」
自分に対する無力感や虚しさというべき印象ばかりの被災地でも、行けば感じ取ることができるものがあったということか。
風化したのは誰の心だったのか
その年のうちに、数回は西宮と神戸を訪ねた。行っても会うのは美術館の関係者ばかりだったが、それでも訪ねることはした。翌年にも震災の時期に合わせて取材に出掛けた。その次の年にも同様だった。年を経るごとに取材の内容は震災から離れていって、美術そのものの話の方が多くなっていったが、「何度も来てくれてありがたい」という言葉もいただいた。
しかし、その次の年には雑誌の企画としては、「もう4年目になるんだから、さすがに苦しいな」という判断で取材の話が流れてしまう。
継続することに意義があるという意見はあった。しかし、震災をテーマにしても、もう記事が売れないという考えの方が支配的になっていた。
風化。メディアの制作現場で進んだ風化。
でも風化したのは、読者の関心ではない。レーティングの数字を読む編集会議のメンバーでも担当の編集者でもない。一番風化してしまっていたのは、自分自身の気持ちだった。どうしても取材したければ押し通す手もあっただろう。それでもだめなら、個人で出掛けて行って記事をつくって売り込むことだってできたかもしれない。
でもそうはしなかった。もうさすがに4年目だからと思っていたのは自分だったから。
「被災」は見えにくくなっていく
最終更新: